カテゴリー: マンガ
-
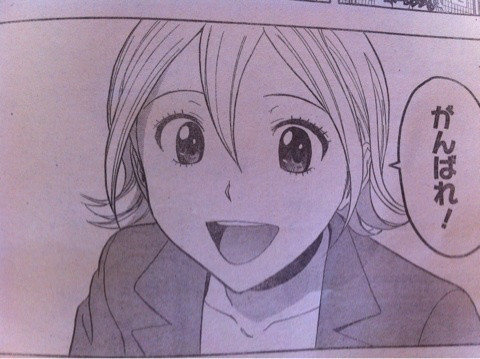
リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より
(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…
-
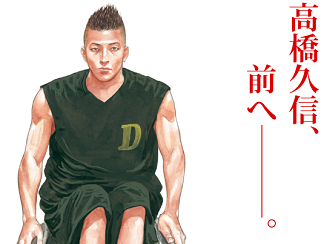
作業療法と 「漫画 リアル」にみる、挑戦すること、失敗を恐れないこと
失敗を恐れて、何かを言い訳にして踏み出せないというのは、人間の性(さが)ですが、そんなことしてたら人生終わっち…
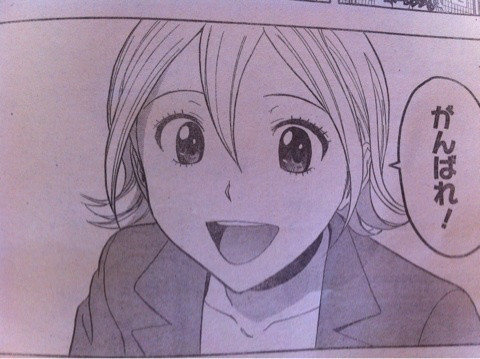
(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…
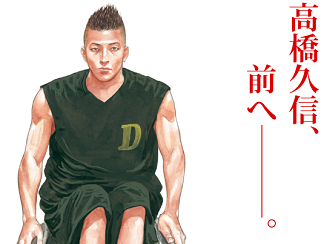
失敗を恐れて、何かを言い訳にして踏み出せないというのは、人間の性(さが)ですが、そんなことしてたら人生終わっち…