カテゴリー: 経済
-
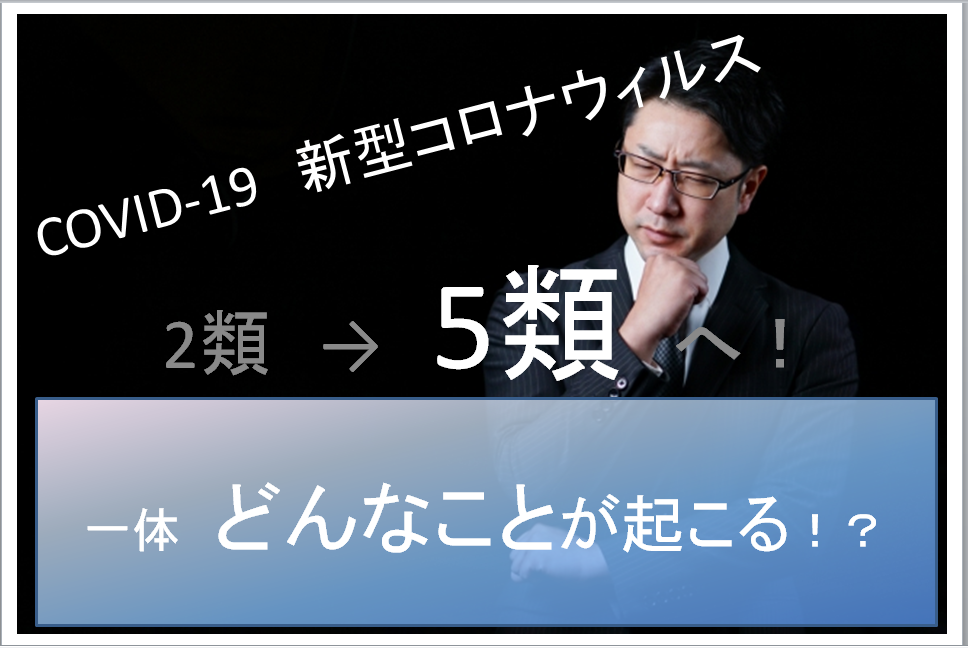
COVID-19が5類になるとどんな事が起こるのか
重要そうな話題があると、一応ピックアップして継続記載してきましたが、今回の話題はどう取り扱ったらいいのか、正直…
-
介護報酬2.27%引き下げと、幼稚園就園奨励費にみる国家の方針
注目していた介護報酬の引き下げ幅は2.27%でした。 国としては、カネを投下してリターンの発生する(プラス成長…
-
介護病棟および老人保健施設とマンパワーの問題の根本的解決法は無いんじゃないかという
はじめに 結論としては、「量が質」だが、量が増えることは無い、という話。 長いですし要領を得ないので、要点だけ…