タグ: 医療
-
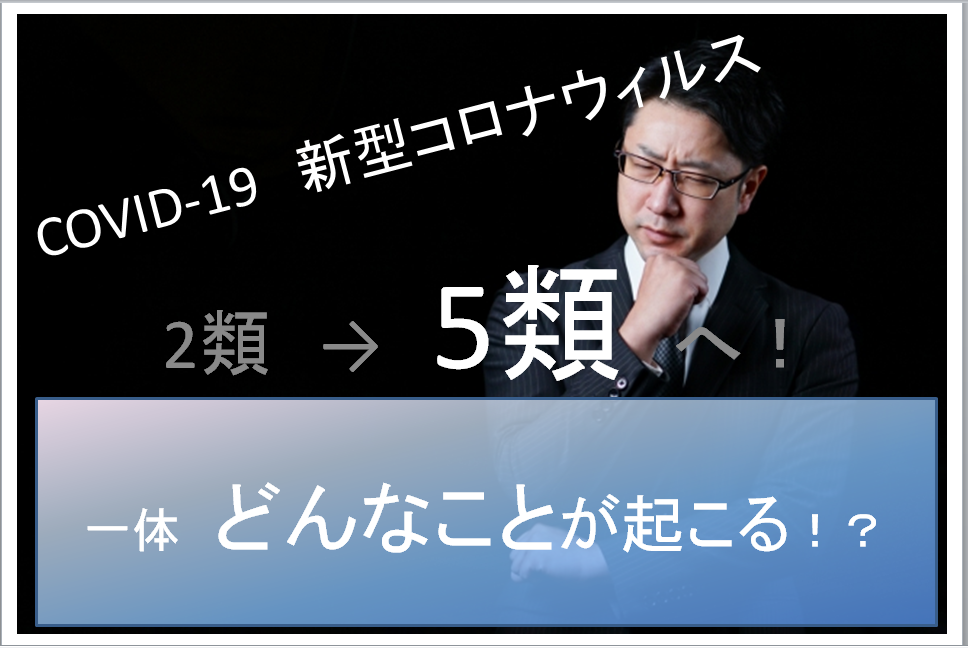
COVID-19が5類になるとどんな事が起こるのか
重要そうな話題があると、一応ピックアップして継続記載してきましたが、今回の話題はどう取り扱ったらいいのか、正直…
-
アメリカにおける精神疾患と医療関係と製薬会社の密接な関係について からの 日本の話
精神疾患と医療と、製薬会社の関係についてのアメリカの記事から、日本も実はおんなじような状況かもしれないことの紹…
-
iPS細胞を使用しての創薬を日本政府が後押しするようです。
iPS細胞を使用した、薬の開発が促進されるようです。
-
鳥インフル「パンデミック可能性否定できず」 from NHK NEWS
中国での鳥インフルエンザ関連のNHKニュースの紹介
-
とてもとても便利な技術は、それを享受する生活やサービスにおける快適さの差を広げる。
焼肉店で老夫婦がタッチパネル式のタブレット端末を使っての注文が出来なくて困っていたことと、それについて思うこと…
-
【3Dプリント】最新3D技術が、医療の常識を根底からくつがえす?【凄い】
新たに出現した、3Dプリントという技術が、今、医療の場面で実際に応用され始めています。作業療法と関わりのありそ…
-
余命を告知することで、訴えられたらしい。
病名を告知したことが、原因となって訴訟された例の紹介。
-
町内会という組織 ~過ちに気が付いた、十年前の五十代と、ある種の諦め~
今後存続しない可能性について。または、地域に帰ってやっていけるようにするとは言っても、そもそもその地域が存在し…
-
「今の日本人にはないかもしれないもの」。あるいは、豊かさと引き換えにして、失ってしまうかもしれないものについて。
中国における、呼吸器介助の一例。
-
続・生保患者診たくないんで、内科医やめる。と言う増田。
生保患者診たくないんで、内科医やめる。 の続きの紹介。日本の生活保護に関する話題の一端。