月: 2016年6月
-
変形性膝関節症の作業療法の基礎知識概要
精神疾患の方って、薬の影響や生活習慣などで、肥満の方がわりとおられます。 ということで、膝への負担が高く、結果…
-

統合失調症に遺伝子の突然変化との相関関係を発見 名大研究
統合失調症の方は、健常者の三倍の確率で遺伝子の突然変異が認められたという研究報告
-
いよいよ第50回日本作業療法学会の事前登録開始。なんと3000円もお得。
第50回日本作業療法学会の事前登録開始のお知らせ。
-
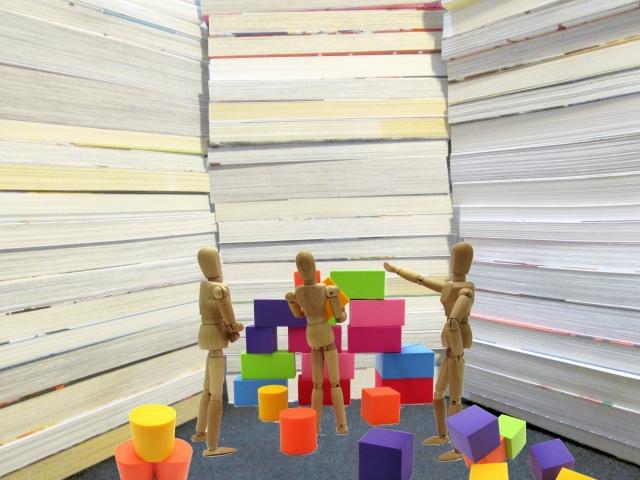
それぞれの作業療法士がそれぞれの作業療法の定義を持っているのがいいと思う理由
作業療法の定義については、当サイトでも掲載しています。 作業療法とは - 作業療法.net ふと、あらためて定…
-
(✿╹◡╹) 〜 全文引用
はてなブックマークで、話題になっていた投稿が作業療法っぽいなと思ったので、引用してシェアします。 (✿╹◡╹)…
-
リハビリテーション職が当事者も社会も元気にするために意識するべき必要なたった一つのこと
私自身、自分が作業療法士になってから、今までの間にいろいろと悩むことがありました…
-
突然の不調 いつもの日常をどのように支えるか
突然患者さんが不調になった。 ということは、よくあります。 …