カテゴリー: 経営
-
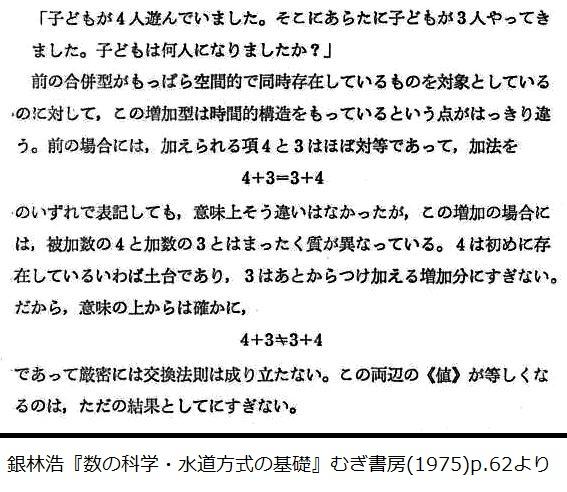
社会と作業療法と効率化を妨げるものの話
作業療法を必要とする人に作業療法を届け続けるために作業療法に必要なのは、イノベーションだと思っています。つまり…
-

今こそ、作業療法士が苦手な「お金の話」をしよう
作業療法士って、お金の話は、積極的にはしません。そこには色々な理由があると多います。そもそも、作業療法の世界が…
-
デイケア送迎問題について特に関心がなかった自分を恥じた
送迎車の事故のニュースについて
-
大手企業が使ってるビジネスの世界のノウハウは作業療法でもつかえるかも?
もちろん、マイナーチェンジやカスタマイズは必要だとおもいますけれど。 でも、正解の確かめ様のないフィールドで結…
-
最近の若いコ中心の介護職のあり方に思うこと
搾取だよね 搾取という言葉がきつければ、一方的に使われてるだけだよね 「若いコがいずれ主体的に動けるようになる…
-
経営的な「ムダ」と医療職である作業療法の持続可能性についての考察 その1
はじめに 「ムダ」をはぶくことによって効率を向上させることには大きなメリットがあるけれども、方法によっては顕在…
-
介護病棟および老人保健施設とマンパワーの問題の根本的解決法は無いんじゃないかという
はじめに 結論としては、「量が質」だが、量が増えることは無い、という話。 長いですし要領を得ないので、要点だけ…