カテゴリー: 学習
-
抜粋「新 作業療法の源流」の序(はじめ書き)
名著の序より。 初めの書き出しには 作業療法の源流の初版が刊…
-
作業療法士が勉強会をするときには、実施前に狙いたい結果を目標設定として掲げるべき
勉強会が始まる前に、「この勉強会の目的って何ですっけ?」と尋ねるのが良いかも分かりません。 作業療法士が複数人…
-
上の人からきいた貴重な経験談ー制度の勉強はとても大切
今日は、病院の重役の方とお話しする機会がありました。 その方から聞いた話ですが、 「業務五年 制度知識が10年…
-
最近の若いコ中心の介護職のあり方に思うこと
搾取だよね 搾取という言葉がきつければ、一方的に使われてるだけだよね 「若いコがいずれ主体的に動けるようになる…
-
作業療法実践の為の学習における各学習項目の価値の理解の重要性。
この記事の方向性 「学校で学ぶことは、いつかは役に立つけど、それっていつかがあんまり分からないままに勉強してる…
-
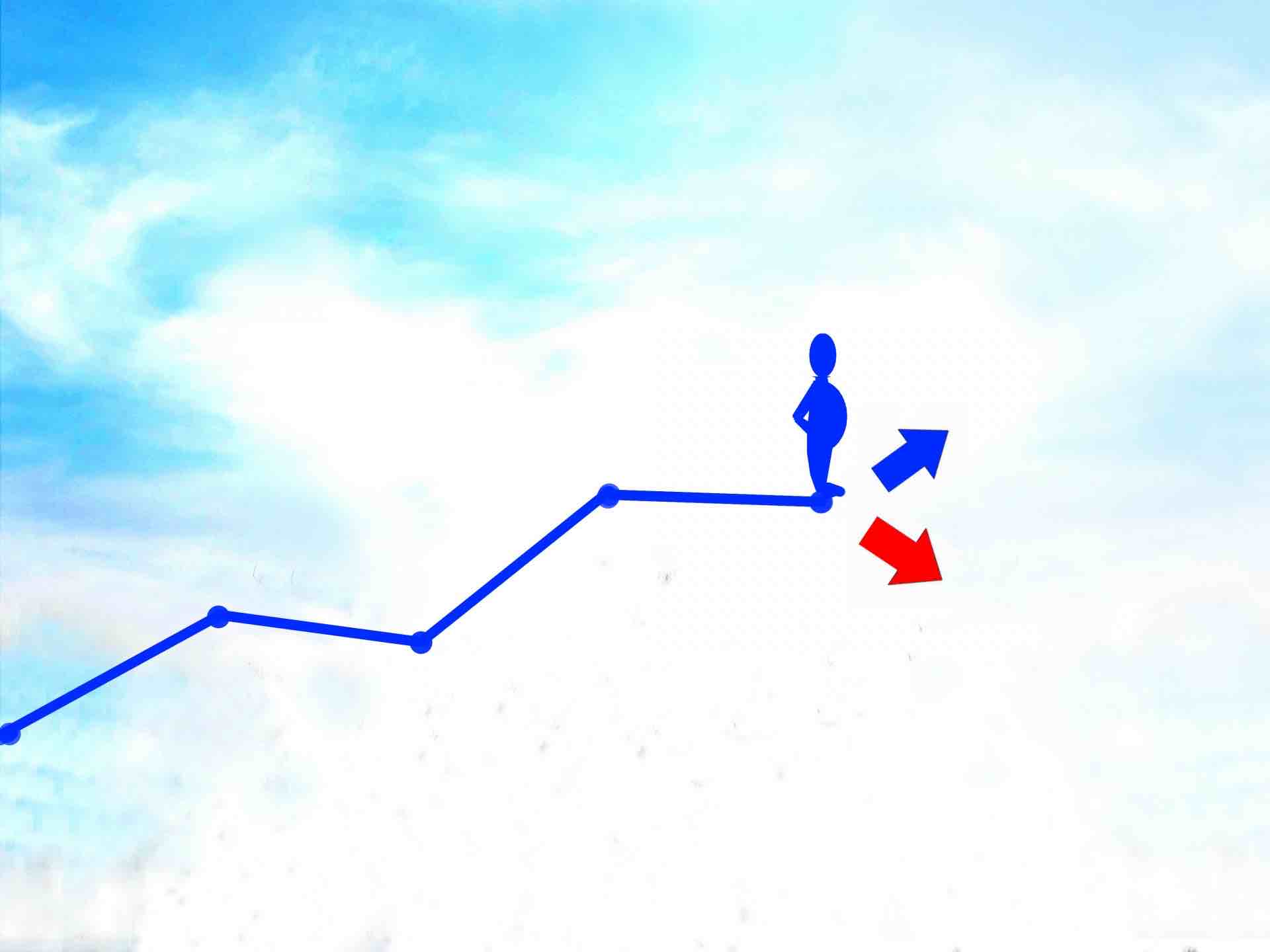
リーズニングという言葉について、作業療法との関連を調べてみた。【クリニカルリーズニング】
リーズニングについてインターネットで検索して調べた結果について掲載しております。
-
知ろう、学ぼう!!COPM(カナダ作業遂行測定)
COPMについて、さわりだけでも学んでみようという趣旨です。