タグ: リハビリテーション
-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編
連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…
-

連載:AIの衝撃 その1 『AIが日常になる』
AIを前提とした日常生活が始まります。 そういう時代になり、これからやるべきことを学ぶ必要があります。 実はも…
-

祝就職いっぷんかんでよめる!?『知っ得』‼️コレからの作業療法士業従事者の皆様へのプレゼント
みんな大好き『知っ得』プレゼント。新卒の皆さんへ先輩からプレゼントです。持っとくと、明日から楽しく作業療法士が…
-

いち作業療法士として、危険だと思う医療・介護・福祉の組織
お金儲けは必要ですが、行き過ぎると、不幸を振りまく存在になります。作業療法士の多くが働く、医療・介護・福祉の領…
-
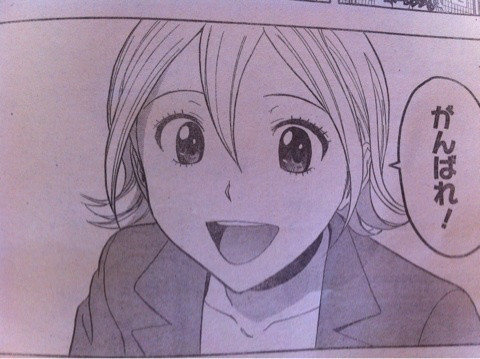
リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より
(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…
-

漫画「マギ」が、壮大な自己決定の話だった件
作業療法にとって大切な「自己決定」の参考書の話です。
-
真実が人を傷つける場合にどのようにそれを扱うかという問題について
真実が人を傷つけるという現象に関して、改めて思った事をつれづれなるままに書いてみました。あまりまとまってないか…
-
フィードバックは大切だ!!でも、実践ってどうするの?そもそもフィードバックって何や?を自分なりに考えてみました。
フィードバックってとっても大事だなあと思ったので、記事にしておきます。
-
日々の気づきを文字化することの大変さについて
自分の体験を、文字に起こすということがたいへんだなぁということと、じゃあどうするかというについての記事。作業療…
-
アルツハイマー型認知症の治療法の最先端二つの紹介+α
アルツハイマー型認知症に関連する最新情報2つの紹介。