タグ: 作業療法
-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編
連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…
-

連載:AIの衝撃 その1 『AIが日常になる』
AIを前提とした日常生活が始まります。 そういう時代になり、これからやるべきことを学ぶ必要があります。 実はも…
-

祝就職いっぷんかんでよめる!?『知っ得』‼️コレからの作業療法士業従事者の皆様へのプレゼント
みんな大好き『知っ得』プレゼント。新卒の皆さんへ先輩からプレゼントです。持っとくと、明日から楽しく作業療法士が…
-

作業療法の論文を、作業療法士は英語で書くべきか?
大相撲の初場所で、白鵬がさすがの勝利を見せて、「ああ、やっぱり強いな」と思った次第です。土俵際でも、落ち着いて…
-

いち作業療法士として、危険だと思う医療・介護・福祉の組織
お金儲けは必要ですが、行き過ぎると、不幸を振りまく存在になります。作業療法士の多くが働く、医療・介護・福祉の領…
-

ぐんま作業療法フェスタ 2018を勝手に拡散する。
群馬県には多分縁もゆかりもありませんが、面白そうなものを見つけたので、拡散します。年明けすぐの作業療法のイベン…
-

今年一年みなさんに最も見ていただいた作業療法.netの記事ランキングベスト10
みなさん、今年はどんな一年でしたか?作業療法.netといたしましては、今年は地獄のサイト移行作業などあり、割と…
-

作業療法業界にはカリスマとエリートが必要
作業療法士であっても、作業療法が趣味の人って、かなり少ないですよね。生活のために仕事として作業療法士してる人っ…
-
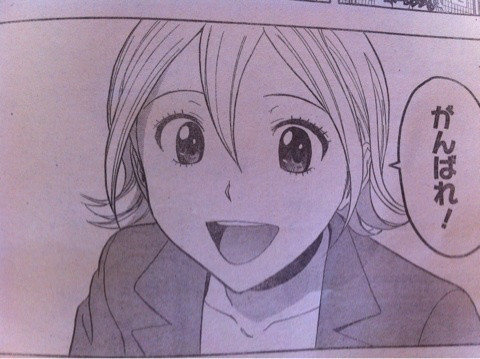
リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より
(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…
-
目に見えないことを取り扱う難しさと重要性 作業療法士に求められること
事象の可視化は作業療法士の重要な専門性のひとつです。