タグ: OT
-

今年一年みなさんに最も見ていただいた作業療法.netの記事ランキングベスト10
みなさん、今年はどんな一年でしたか?作業療法.netといたしましては、今年は地獄のサイト移行作業などあり、割と…
-

作業療法業界にはカリスマとエリートが必要
作業療法士であっても、作業療法が趣味の人って、かなり少ないですよね。生活のために仕事として作業療法士してる人っ…
-
『患者様の状態に「感覚」で共感することが難しい』という悩みについて
「患者様がどんな感覚なのかが今ひとつわからないから困ってる」という悩みについてひろえもんなりに考えを書いてみま…
-
移乗の介助のときに現場の人が腰痛にならないために、必要だなあと現場の人間として思うポイント「移乗知っ得ナレッジ&テクニック」まとめ
ひろえもんなりの移乗時の腰痛防止ポイントについて
-
昨日先輩に「いっぱいいっぱいか(笑)!」と言われてハッとした話とか
新人作業療法士(OT)が、就職後3週間働いてみて、いろいろやってみて、その間に思ったこととかとか。
-
とある新人作業療法士(Occupational Therapist:OT)の卒業から就職までの流れと、就職後一週間の概要
とある新人作業療法士(Occupational Therapist:OT)の卒業から就職までの流れと、就職後一…
-
OTS(作業療法士見習い)としての自分の感覚が相当世間ずれしてきていることにいまさらながらに気が付かされた出来事について
OTSとしての自分の感覚と、世間の実際の認識の間に、いつの間にか大きな隔たりがあることに気が付かされたことに端…
-
知的障害者が看護アシスト 国立がんセンター東病院
知的障害者の就労の拡大と作業療法における評価技術に関する妄想。
-
親が「我が子のいじめ」に対処する難しさ いじめ相談サービス(by法務省)への感想
いじめ問題を子供がダイレクトに専門家に相談できるという内容の、法務省がやってるサービスに関する記事を読んで思っ…
-
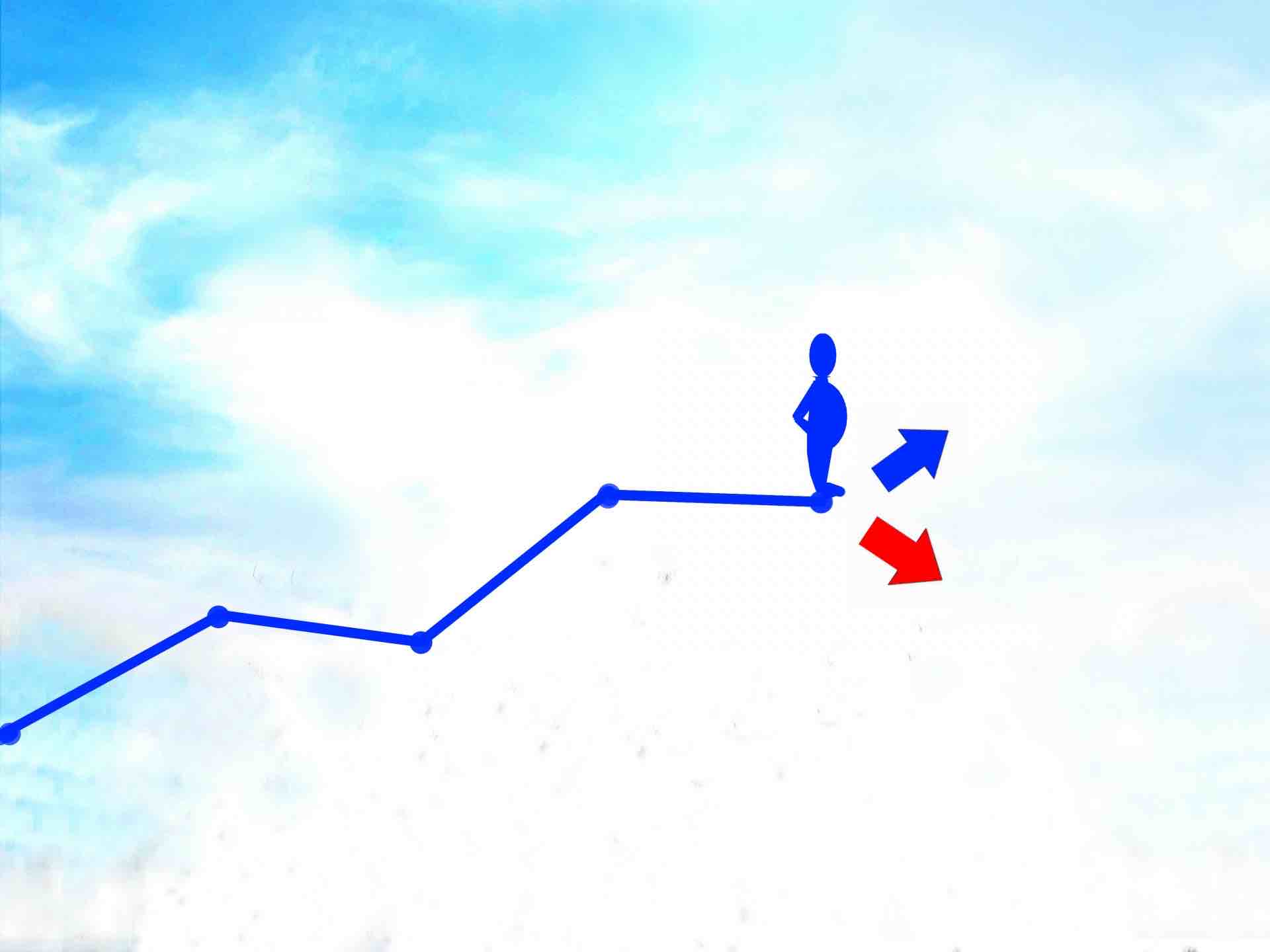
リーズニングという言葉について、作業療法との関連を調べてみた。【クリニカルリーズニング】
リーズニングについてインターネットで検索して調べた結果について掲載しております。