カテゴリー: 作業療法学
-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編
連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…
-
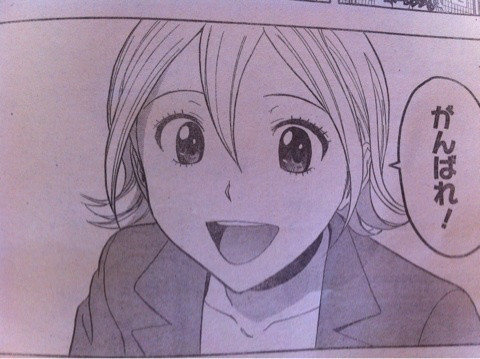
リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より
(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…
-
作業療法士の立場は、治すことではなく癒すこと
治らない病や怪我を生きる人が、前向きになれるように支援をする。 それが作業療法士のあり方や、役割です。 治すこ…
-
社会と隔絶されていたら、作業療法じゃない
作業療法とは何かということを、社会参画に関する側面から見てみます。
-
作業という言葉、たぶん普通は専門用語として理解出来ない
作業療法士が用いる、「作業」ということば 作業療法士が用いる「作業」という言葉は普通の作業と意味が違うのです。…
-
今や「理学療法は生活動作の専門家です」らしい
facebookで流れてきたので気になって調べたら、こんなポスターが。 http://www.japanpt.…
-

作業療法における研究エビデンスの質の考え方
エビデンスに基づく作業療法(EBOT)は、エビエンスに基づく医療(EBM)のひとつであり、現在ホットな考え方で…
-
作業療法士の役割は、作業と人の媒介になること
はじめに 作業と人は不可分のものとして良く説明されるし、そのとおりだと思う。 しかし、ひょっとするとあえて独立…
-
作業療法の考え方をすべての人が掴めるようなコンテンツを作り、受け取ってもらうには 言葉編
はじめに 作業療法の考え方を表現するときに、OT語を多用していませんか。(ひろえもんはついつい使ってしまいがち…
-
作業は「できりゃあ、なんでもいい」という物でもない
この記事を読んで、作業について改めて考えさせられました。 はじめて逆上がりが出来た女の子:成功後の一言が指導者…